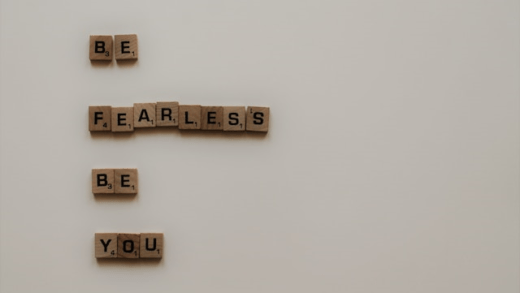学域に関しては、The top of the heapsの先生がたから教育を受けたので。東大に関しても、ふーんとなりますし、京大に関しても、ふーんとなります。
地味に強度が高かったので、大学ランキングみたいな(世界の大学ランキングは基本的にコモンウェルスの覇権上に成立するものでした。無意味もいいところですよ。最近のは興味がないので知りません)ものにも興味がなく。
へぇーってなります。知らないものに関しても、専門に関しても。

最近、村上春樹さんの新しい小説が刊行されていますが。
私は、残念ながら、エッセイストとしての村上春樹さんをものすごく評価しているのです。小説になると、さっさかと読んで、それでなんだったんだろう?という、とても辛口の読者になるのです。
すみません。申し訳ありません。
だったら、古典文学の方がいいと思ってしまったり。
やっぱり、文体については、ある程度の修辞がないと日本文学は読まないんです。
だいぶ前に自分の先生と雑談をしていた時に、あ、○○先生は新しい本を書きはったんですねーと研究室で先生の本棚を眺めながら話をしていた時に。
日本のありとあらゆる分野から、修辞がなりをひそめる最中だったので。先生によると、編集者からダメ出しの嵐で、修辞がダメになっているという話を伺っていたんです。
編集者から文体をなおすように言われたらしいよっと先生が残念そうにお話になっていて、悄然としました。

私が尊敬している先生の当時の新しい著作が研究室の本棚にならんでいて、多分、謹呈の本なんだろうなぁーと思いながらお話をしていた時だったので(謹呈の短冊が挟んである著者の先生から関係者の先生方に送られる本のことです。先生に本を借りると挟まっている場合があり、借りている間中無くさないように、取り扱いに少しだけ困る短冊です)、かなり悲しい気持ちになったのを覚えています。
別の個人的に尊敬している先生の本の話で、その残念な話を逸らそうとしたときに、あー、雑誌の掲載の時にはもっと凝った文体だったのを、本にまとめるときにわかりやすくしてくださいって、編集者に頼まれたらしいよーという話を聞き、凄く好きな著作でもあるので、あれよりも雑誌の掲載時には凝った文体だったんだ、うーん、そっちを読みたいけど、もう無理という状況でした。
最近では、本を購入する際は、あー、文庫になったんだ、もう読んでるけど、文庫だから買うという購入の仕方になっています。

内容が薄い本については、とても冷たい姿勢を持っているんです。
購入して、内容がない本の場合、購入したのでやっぱり読むんです。私に「積ん読」用の本はないので、読みます。
そして、猛烈に腹を立てて、おしまいになるので、もう最初から読まないようにしています。
どの本が内容があるのか内容がないのかぐらい見当はすぐにつきます。
専門性の高い先生に囲まれて、育ったので、つまらない本に関しての態度は、本当に冷たいのです。それが、思想書だろうが、小説だろうが一緒です。英語で読んだ方が安い場合は、英語で読みますし。最近の小説って、英語圏でもそうなんですが、なんでこう、読みがいがある文体がないんでしょうね。
じゃあ、どんなものが?という、あなたの疑問に応えたいと思います。
例えば、短編でもいいんです。コンラッドみたいな文体の本は最近ないでしょう?
あの頭の中で日本語に置き換えようとすると結構、むつかしい英語の文体をもつコンラッドです。

私の先生の専門はコンラッドではないのですが。先生の読み解くコンラッドの世界は凄かったんです。先生、論文書いたらよかったのにと思うほど、深みに満ちていました。学部時代にコンラッド専門の先生の講義を受けて(学外の先生です)、ウンザリしていたので、とても勉強になったんです。
基本的に優れた先生について勉強に励むという姿勢に勝るものはないです。
ただし、先生のトレースはダメなのです。そこから、自分はどう別の立脚点に立てるかという課題がでるので。私の場合は、立とうとする最中に心を壊したので、むつかしかったですが。
例えば、Youth, A Narrative; and Two Other Storiesという作品がありますが。短編集です。
Youthだけでも、きちんと心に刺さってくる、おそらく読者の年代関係なく刺さってくる内容を持っています。
読書量だけは、嘘はつきませんし。質のいい教育も嘘はつけません。
日本の大学を国公立大学はそのままに、私大を圧縮して、教育費を無料にして、その授業料自体は公費にしますとすると、日本の教育水準は元々低くはないので、凄くいい政策になるはずなんです。ただし、国政からすると、自分の頭でものを考える国民を必要としていないので、そこまでの施策が打てないんですね。で、結局、奨学金で苦しむ社会人を一定数出しても国会で重要な議論になっているのかさえ、定かではありません。どうでもいい公金の使い方はするのに。以前、高齢のホームレスの全人生の面倒をみますというNPO法人の取材をNHKで観たことがありますが、あ、これ関西でいうとこの、たこつぼやんっと思いました。ホームレスのひとは無理やり生活保護の受給を迫られて、その生活保護費のほぼ8割ぐらいを、NPOに中抜きされるという取材内容でした。取材されているNPOのあくどさに全くNHKの取材側が気づいていないという。そのNPO法人に収容された皆さんの手持ちのお金は受け取る生活保護費のなかの1~2万円とのことでした。要するに貧困ビジネスで、生活保護費の中抜きをしていることになります。他の支援の仕方があるんじゃないんだろうかと思ったのですが。主催しているNPOのひとによると人件費もいるし、なんたらかんたらと自分たちの都合が最優先みたいでした。国から補助金貰って施設を作り、運営しているそうです。日本の貧困に巣くうNPOのビジネス展開の暗闇について、空恐ろしい気持ちになりました。あらゆるところで搾取の仕様だけ構築されている日本の現在地をみて、本当に怖い思いをしました。ある日、貧困に陥ると、日本の場合は、役所が本人に対して、親類縁者に支援ができないか連絡を取りまくり、目の前のひと一人の人権を全否定するというのがお役所仕事の通常なんだそうです。虐待のケースとか念頭にないんでしょうね。大学の研究の助成金の透明性も確保されていないのは、徳島大学の件で理解しています。SNSの情報でうんざりしました。「ヒトの味覚の嗜好は6~8歳までに決定」という文言で、あ、この大学は死に体だなと思ったんです。大学が世間に開かれた場合、このような研究の貧困は起こりえないでしょうし。国公立の大学に関しては、全額無料にしなくとも、講義別に大学が勘案して、聴講無料にするといいのではないかなとは思います。そこに税金をかけるんです。大学を閉ざすのではなく、一部を完全に開放するとここまでの見苦しさというのはなくなるのではないかなと思います。国連の施策と何の関係もありませんからね。