人口減少問題という問題が取り上げられて久しいですが。
どうなんでしょうね。実は、NHKとリクルートで真逆の視点があるんです。
まず、NHKからですが。
日本の人口問題 有識者が提言「2100年に8000万人目指すべき」 | NHK | 少子化
だれが、問題視しているかという点は置いておいてください。問題は、他の先進国との比較の視座がゼロという点になります。
一部引用をしておきます。
厚生労働省の「国立社会保障・人口問題研究所」は2020年の国勢調査の結果を基に、日本の人口が2056年には1億人を下回り、2100年にはおよそ6300万人に半減するという推計をまとめています。
こうした中、日本商工会議所の前会頭の三村明夫氏や、日本郵政社長の増田寛也氏ら有識者のグループが記者会見を開いて人口問題に関する提言を発表しました。
提言では、このまま急激な人口減少が続けば市場の縮小によって、あらゆる経済社会システムが現状を維持できなくなり、先行して人口が減少する地方で消滅する自治体が相次ぐと指摘しています。
そのうえで、おととしの時点で1.26となっている合計特殊出生率を、2060年に人口を長期的に維持するのに必要な2.07に改善させ、2100年に人口を8000万人の規模で安定させて成長力のある社会を構築することを目指すべきだとしています。
そして、内閣に司令塔となる「人口戦略推進本部」を設置するほか、有識者や経済界、地方自治体などが自主的に参加する「国民会議」を立ち上げて、総合的・長期的な視点から議論を行うとともに官民挙げて対策に取り組む必要があるとしています。
NHK
子供を出産すること自体が保険適用もされていないのに。そんな先進国は他にありますか?2026年に保険適応にするということが閣議決定はされていますが。制度設計を組まないと保険適用できません。
要するに、怪我や病気ではないから、保険適応はしないんだそうです。議論としての主目的を間違っていると思うのは私だけでしょうか?
騒いでおきながら、自由診療って、そこやろ、根本的な見直しはと思うのは、私だけでしょうか?

リクルートはめずらしく、別の方向からの視点を提示しています。しかも、京都大学の精神科医の視座をもって。視点は一部私も全く同意です。こういうときは、京大が頂点の場所の教育環境で育ったんだなーって実感をします。
「人口減少社会は希望だ」京都大学広井教授が考える、成熟社会に生きる私たちのこれから | 株式会社リクルート (recruit.co.jp)
なぜ、広井先生(すいません。著作は読んでおりません)がリクルートの取材を受けているかというと、日立京大ラボの研究の宣伝のためです。それ以外ではないです。
一極集中の人口動態の問題に関して、分析をかけたそうです。解析ではないですよね。
「AIを活用した「2050年の日本の持続可能性」についてシミュレーションを実施しました。そこでは「社会を都市集中型か地方分散型のいずれに進めるか。それが日本の未来にとってもっとも本質的な分岐点になる」という結果が出ています。」だそうです。
私が広井先生の視点に同意するのは、この部分です。
歴史的に見れば人口が右肩上がりに上昇を続けてきたこの100年間は、むしろ特殊な時代でした。日本の人口は、794年に都が平安京に遷都して以降、ほぼ横ばいで推移していました。江戸時代に入り若干人口は増えたものの、3,000万人程度に落ち着き再び横ばいに。それが明治時代から急激に増加をはじめ、太平洋戦争時に一時的に減少しましたが、戦後の復興と高度経済成長期に再び爆発的に増加。グラフにすると、ほぼ垂直に伸びているような図になります。
また、他の先進国と比較しても、私は日本が1億数千万人でなければならない合理性はないと考えています。例えば、イギリス・フランス・イタリアはいずれも人口6,000万人程度で、ドイツは8,000万人。国土の面積が異なるため単純比較はできないものの、1億人を割るから国が維持できなくなるとは必ずしも言えません。
リクルート
そして、同意しない点は以下の部分です。
今日本の各地で個人・NPO・企業が連携した地域再生の動きが出ていますよね。彼らは持続可能な社会を実現するためという、従来の利益至上主義ではない思想でコミュニティを形成しています。
そうした集団の枠を越えたつながりや拠り所を考える場合に、私は「自然」がひとつのポイントになると思っています。これは、日本で古来より存在していた自然信仰とも共通点が多い。私は「鎮守の森コミュニティプロジェクト」という企画をささやかながら進めていて、「鎮守の森コミュニティ研究所」を運営しています。
「八百万(やおよろず)の神様」という発想ですが、いわゆるパワースポットへの関心もあってか、各地の神社などを訪れると、意外にも高齢世代より若者の姿を多く見かけます。人口減少時代とはそうした伝統文化をもう一度発見していく時代でもあると思います。
リクルート
結局、ムラ社会に回収するという視座になるので、社会問題として解決しないのです。
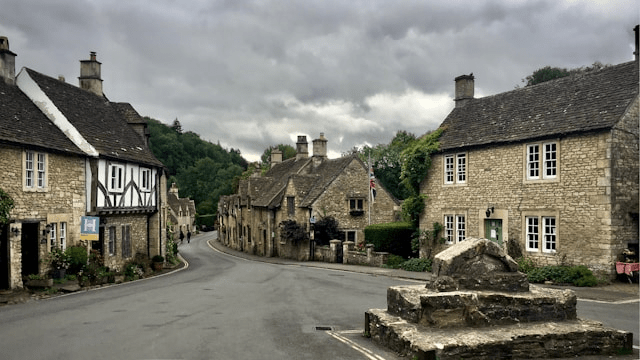
私が育った場所では、ムラ社会特有の面倒くささもあるんですが、基本的に、他地域ほどムラ社会特有の制度設計を住民に上から強要しない場所だったんです。
いざとなったら、ちゃんとしなあかんけど。どこでサボるか、どこで落としどころを探るかという視点も大事にする社会構造です。
山があるんですよ。当時、ニュースで見て、凄いなぁーとおもったんですが。毎朝、朝に山まで登る趣味の人たちがいるんです。山にある施設では記録をつける紙が貼り出されていて、何時に誰が来たという事がわかるそうです。年配の方のほうが、経験値の分だけ、成績がいいんですって。当時はそうだったんです。いまは知りませんが。頂上まで行くわけではなさそうでしたよ。
議論の場所は作ろうとしますし、落としどころも探ろうとします。でも、それを言い出したら、どこの自治体もおなじですけどね。ちゃんとルールは守ろうとはします。習性なのかもしれません(嘘です)。ただし、自分が持っている感情の押し付けはしないんです。自他はきちんとしてます(他地域に住むまで知りませんでしたが)。
自然という部分では共通点ですが、大学の先生がいちから作り出さなくっても、大体整備済みだったりします。
私が育った場所では、拠り所に対して、強制的姿勢を取る姿勢を強いられると、逆にあれはなんやという発想になるんですよ。強制ってなに?怖いなってなります。
行きたいやつだけいったらええやんという発想です。
私の場合は、ベンゾジアゼピン離脱症候群からの逆算の行動になるので、ほぼ感情労働です。
しんどいです。ひとりでぼぉーっとする時間を大事にします。
ベンゾジアゼピン離脱症候群と向き合う皆さん、ちょっといいこというてんなぁーという精神科医に騙されないように頑張りましょうね。精神科医がやりたいのは、観察という名のストーク行為です。端的にいうと。観察で患者が治れば話ははやいねんけど、無理やなって思ってます。投薬の手前のアイディアがゼロなので無理やろなって。既存でさまざまな場所がありますから。それをいちいち主治医に報告する義務もないですよ。薬漬けからは、早めに逃げをうちましょう。




