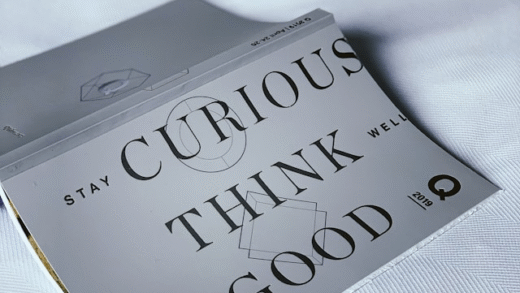普段は滅多に本屋さんで購入しない本に、新書という形態があります。新書サイズの小説があるくらいですし。
読みやすい形状なのかな?とも思ったりもします。
手に持ちやすかったりするのかな?って。

普段、なんで新書に手が伸びないんだろうとも思うんですが。
たまに購入したりはするんですけれどね。
わたしのなかで新書に勝手なイメージがあるんです。単行本の内容をわかりやすくかみ砕いた本というイメージです。いまでもそうなのかはよくわからないんですが。だったら、それにいくらか上乗せをして、文庫本を買ってしまうんです。
内容が濃い文庫本はあるので。
単行本で持っているというのが文庫本で出たりもする最近なので。
文庫本を探して購入したほうが、個人的にはお得感があります。
選んで購入しますよ、もちろん。
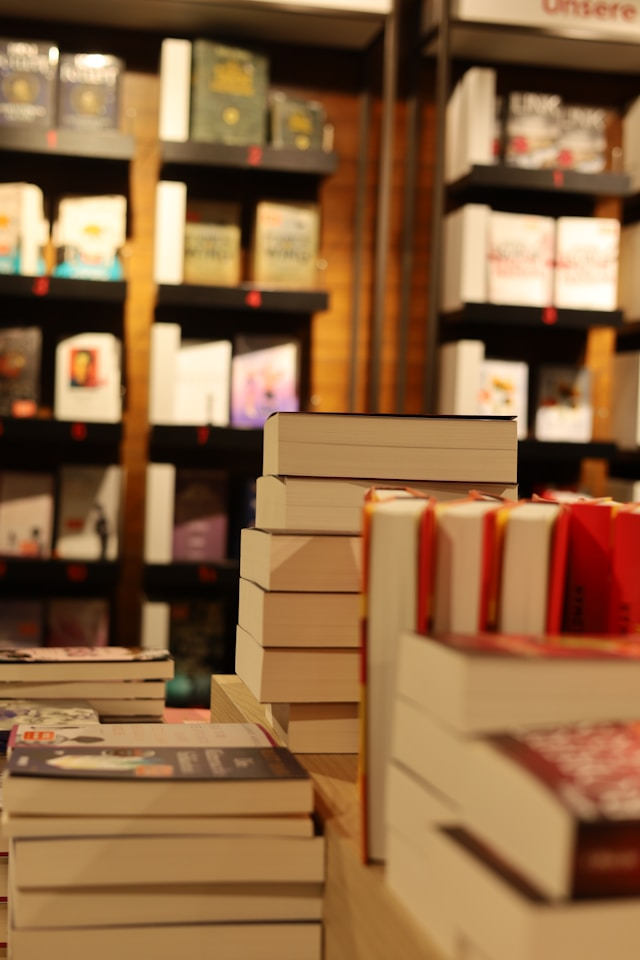
本を読む体力が出てくるといいなーとは思っています。一昨年くらいにガタンって落ちたんですよ。減薬の最終段階の手前で、落ちましたね。通常の体力が落ちたのでしょうがないのですが。
だからって軽い内容の本を購入しても読み流して終わりですし。
小説に関しては日本の作家はもうかなり限られるのもありますし。最近の流行の作家とか全く読みませんしね。興味がないんです。
日本の作家が不得意というわけではないんですが。独特の湿気を感じることがあるんです。日本は湿度が高い気候でもあるので、それで文体に反映でもされるのかな?って思う時もありますが。必要な描写と不必要な描写のアンバランスがあると、どうしても気になるんですね。気になってくるとずっと気になって読んでいる間じゅう気になって。なんなんだろう?この時間はって思いますし。
海外の文学でもありますよ。ステープルドンの『スターメイカー』の擁護はしたいんです。翻訳がとても誠実なのは理解できますし。戦争前夜のサイエンスフィクション(ステープルドンにSFを手掛けた自覚があるのかは話は別ですが)ですし。再読には耐える内容になっています。

好んで読み直すひとは限られてくるかもしれませんが。
現代のひとが、或いは科学者が考える宇宙も仮設の域は出ていませんし。原初の宇宙はだれも見たことがない時空になります。現代の宇宙の基礎的な知識と、地球についての本当に基礎的な知識だったり、進化論の基礎的な知識を総動員して読んでいると、人間と遠くにいるのかもしれない地球みたいな生物がすんでいる惑星を想定したときに、考えすぎているんじゃないのかな?とか。
わたしは、サイエンスフィクションは好きなジャンルなんですが。
割と勢いにのまれずに整合性を加味しながら読むほうなので。
そのような生態だとこういうほころびがとか。だから数ページで描写を終わらせているんだろうか?とか。ご都合主義的な部分に関しては目をつぶらないんですね。
コスモスはおそらくこういう概念なんだろうけれど、それと作品を覆っている宗教観への拘泥はどうなんだろう?とか。
どうしても突き放しながら読み進めるので。
アンバランスが気になると、そのアンバランスに対する違和感というのは極めて大事にしながら読むんです。
大人になるって残酷なんだなって読後に思ったりもしました。

戦争前夜からは距離はとれないので、描写のなかににじみ出ていますし。それはしょうがないんです。時代性から文体を切り離すというのは至難の業になりますし。
ただ、これだと大文字の文学には組み込まれないというのは理解できますし。
読みながらすごくもどかしかったです。
久々にステープルドンの未知の小説を読みながら煩悶するとは思いませんでしたが。
いろんなひとがインスパイアされる内容になっているというのは理解できるんですけど。遠大な時系列を扱うのであれば、隙間はくまなく埋める作業をしないと、整合性が軋み出しますし。
もう少し冷静さがほしかったです。惜しい作品でした。
たまに英語でこの部分は何になるのだろうって思うんですが。中途半端なペーパーバックを購入してしまうとそれこそ、お金の無駄になるので。そこは今回は我慢をしました。
注釈のしっかりとした版をイングランドのどこかの出版社が今後扱うことがあるのなら、読んでみたいなとは正直思います。
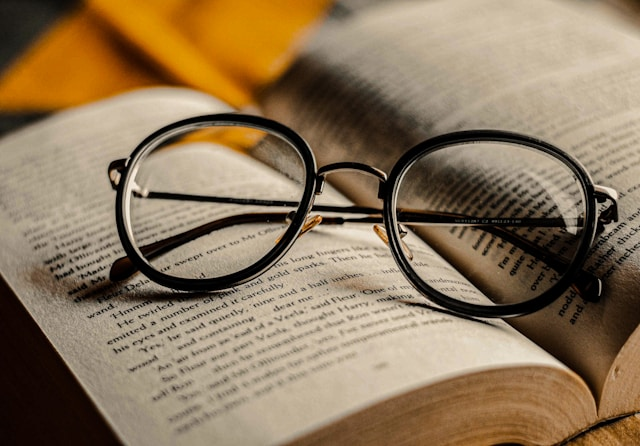
しっかりと読むので、長さ自体は苦にならないんですよ。内容が濃かったらその分、何日でもその世界を楽しめるわけですし。みっしりとしたものをしっかりと読むのが好きなので。購入したことは後悔はしていませんが。これは買いだったなという作品では、いまのところないです。
さくっと読める作品だと、さくっと読んで終わりですし。
みっしりしていたとしても、中身の整合性の齟齬があちらこちらにあって不協和音みたいになっていると、悩みもしますし。
サイエンスフィクションに整合性を求めてもなんですが。サイエンスフィクションなりの整合性って必要なんです。
簡単に、この作品には大満足という小説には出会えないということです。
好きな作家はもちろんいますし。世界観に耽溺できますし。例えば、ボルヘスなんて大好きなんです。海外小説の単行本を読み始めたのがボルヘスあたりで、辞書を引いて書き込みしながら読んでましたし。
わからなかったら、わかるまで繰り返して読むという基本姿勢を持っています。
基本的に投げ出しません。
なので、新書という形態はむつかしいんですよ。わたしにとっては。
丁寧でわかりやすい姿勢というのは大事になりますし。それでも購入してきた経験から言及すると、結局、新書の形でそこに詰め込める限界点とそれに抗う姿勢に延々と付き合うって、ある意味しんどいんです。だったら、しっかりとした別文献の文庫をよんでいたほうが安心感があるんです。理由はあるんです。また、新書形式でいい本は過去購入もしています。現在の流通がないだけなんですよ。