哲学書なんか読んだりしますよ。普通に。
別の先生に、あなたたちは文学理論って言われてもさっぱりでしょ?まず、Aというテクストを読んで、わからなかったら、Bというテクストを読んで、それでもわからなかったら、Cというテクストを読みなさいと指導を受けたこともあります。
17世紀の戯曲がテーマでした。ペーペーだったんですが。翻訳が岩波にあるからということで、翻訳を読んでもいいよという許可があり。テクスト読了後は、先生に渡された論文を次週までにまとめて発表するという講義内容でした。論文をしっかりと読んだのは実は講義がはじめてで。しかも先生による細かな指導付きだったので、今考えるととてもためになった講義でした。毎週、論文と格闘するという。実際は朝から晩までテクスト読解に明け暮れてましたから。

実際に文学理論を読んでいると知らないことだらけなので、単に更に読む文献が増えていくだけなんですよ。かなり、一方的に増えていきます。
これはわからないなって思い、最初に文献に手を出したところで挫折するんだろうなって思って。
新書を選ぶんです。新書を読みながら、新書という形式はむつかしいんだな、全部書き尽くせないという頁の限界があって、どこをどうやって道筋をつけるのかがむつかしいんだなって思いながら、わからない箇所もあるので。
先生に質問するんです(複数形です)。先生、文学理論の本を読んでいて、ここの箇所がわからなくって、むつかしいんだろうなって思って、この新書を読んで、余計にわからないんですって。
すると、頭から怒られ、怒られ、怒られます。
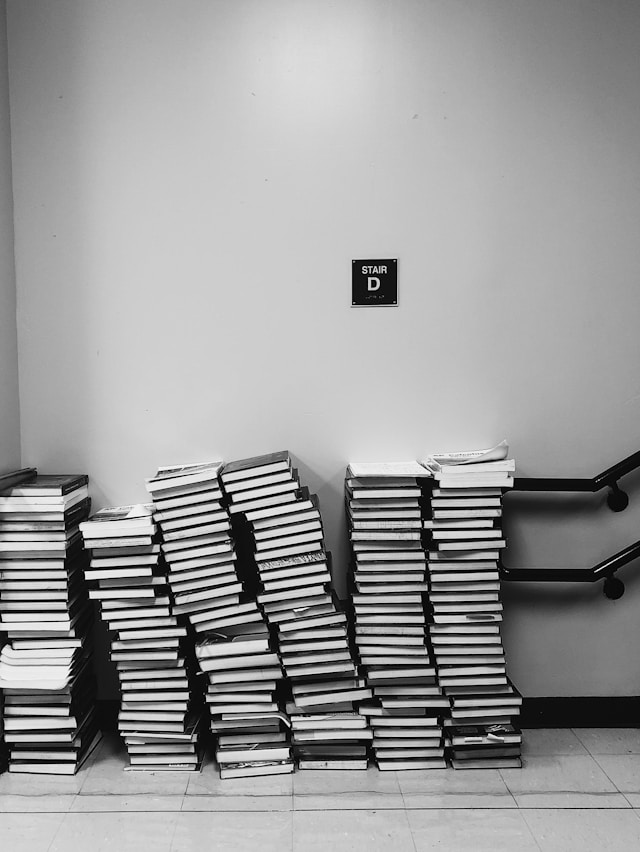
なんでそんなくだらない本を選んで読むんだとか、なんであんなやつの文献を読むんだとか、もっとテクストをきちんと読みなさい。あんな本は読まなくっていいんだから。
お説教の嵐に飲み込まれるわけですよ。
要するにテクストを読んで悩みなさいということです、くだらない解説本なんて意味がないからっという怒られかたです。
もう、嵐が過ぎ去るのを待つしかないんですよ。
ほかに手はありません。
先生(複数形です)は基本的に学生に詳しいので、まっとうな指導しかなさらないんですね。
わたしの目的のための手段の構築の仕方が完全に間違っていたということです。
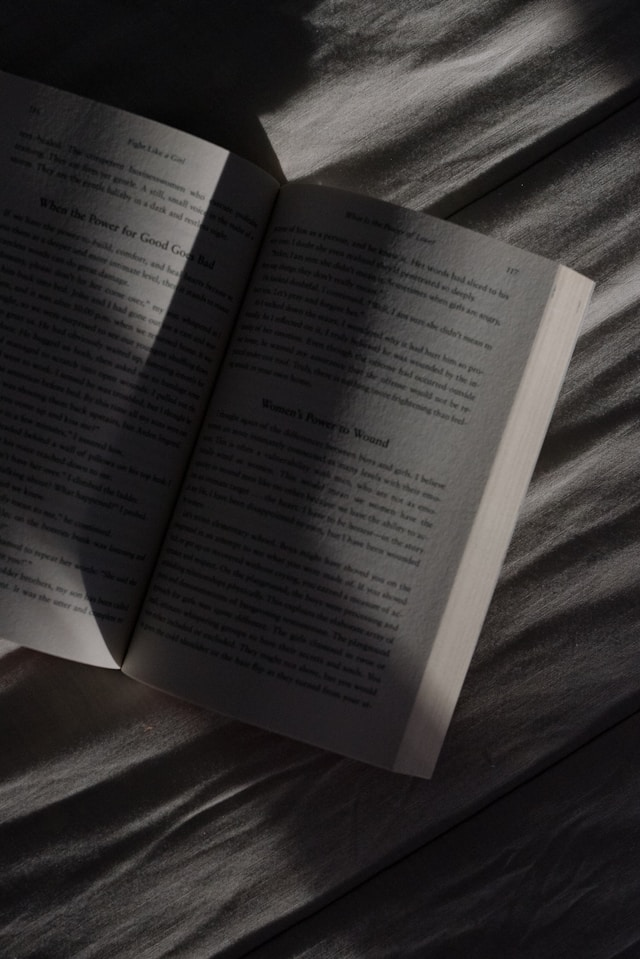
そして、こんな本を読んだことがないというところからはじまるんですね。
全く哲学書になじみがないわけではないんですが。文学理論に組み込まれているような文献に関しては読んだことがなかったんです。まったくではないですが。過去に読んだ本で批評理論に間接的に組み込まれている文献であっても誤読している可能性はあるわけなんです。
読まないと最終的にはどつかれるんだから(比喩表現です)、どうせ怒られ続けるんだったら、あきらめて読もう、それからわからないところを悩んで質問をしよう、とりあえず、選択肢がもうないというところからのスタートです。教えてくださる先生はいて、指導方針もあり、そこに乗っ取って本を読みだすんです。無論、翻訳文献ですよ。
とにかく、どんって読みだすんですよ。
いまでも思いますが。ある意味、量を読むということは大事なんだなって、そのときに学んだんです。
文学理論上では、手段として扱われているんだろうけれど、細かいところがわからない場合の、虎の巻というのもあったので。それはそれで役に立ったんです。その本を参考にしていることは先生にはちょっと内緒にしていました。
読んだ本で、更に怒られるのは結構堪えますからね。
ただ、この哲学の文献というのは、批評理論という作法にのっとると、こういう風な、ある意味、奇妙な、そして特徴のある用いられ方になるんだなというのは学べました。完全なる手段のための哲学ですよね。
意味があるのかどうかに関しては、むつかしいと思います。

批評がイズムになるときには、束になって扱われるんですが。それぞれ別のテクストになるんですね。それぞれでひとつひとつのテクストです。
丁寧に読んでいくと、このテクストとこのテクストにはこういう齟齬があるのに、こういう違いがあるのになんで乱暴に束にしているんだろうという瞬間は随所にあって。
この文学理論のテクスト自体が、誤読を蔓延させるもとになっているんじゃないのかな?という乱雑さになります。
学んだ先生がたにはその点に関して一律で怒られたんだろうなって思っています。
有名なものに、ラカンがポーの短編小説「盗まれた手紙」を援用した講義があります。
ポーが書いた探偵譚を図式化して、そこにラカンがフロイトの概念を援用にしながら、壮大な(ある意味壮大ですよね)な読み込みをするんです。
では、わたしは専門ではないのですが、実際にポーの研究者が「盗まれた手紙」を精読読解するときに、ラカンの講義のような読み解き方をするかというと、まずそれはないんです。

ラカンは精神分析学の視点から思考の手続きをわかりやすく伝えるために、ポーの探偵譚を利用して、説明するために短編のテクストをわかりやすく再構築して、図式化しています。
おそらく、ポーの研究者は一言一句分析対象にします。テクストの精読読解というのは、ひとつの単語でさえないがしろにできないからです。
ラカンにとってポーのテクストは自分の考え方を伝える手段にすぎません。
ポーの研究者にとっては、「盗まれた手紙」というテクストはポーの探偵譚という総体のひとつであり、また一つのテクストになります。そこを詳細に読解してポーの意図というものを解き明かさないといけないんですね。
アプローチが全く異なるんです。
ラカンが適切にポーの探偵譚を読解しているかどうかは、おそらく精神分析学からすると二の次になるのではないのかな?と思います。
当たり前のことですが、ポーはラカンに自分のテクストが読み解かれるようには短編を書いてはいません。
ラカンが整合性のあるレクチャーを行っているかが焦点だと思います。
手段が目的になるケースを読み落としてはだめなんです。
一瞬、きれいな読み解き方に読めてしまうのかもしれませんが。手段と目的を混同してしまうと、過ちのもとにしかなりません。
ただし、文学批評を形成するひとたちが、すべてラカンのような姿勢なのかというと話は別です。

信じられない綿密さでテクストを読み解いたうえで、レクチャーを行う哲学者もいます。実際にいます。
文学批評になると、そこに登場してくる論客というのはグラデーションを描くんですが、グラデーションを描くということは、束にしているので、それぞれで詳細な捕捉ができないということの現われでもあります。
文学批評のこのテーマという形で、わかりやすくとらえるというのが、時折危険になる瞬間はあるんです。
勉強する皆さんは気をつけてくださいね。
先生に塩梅を取られてしまった論文を、ほかの先生がこれは、誤読だよねっ、誤読してるよねって詰めてくる場所で勉強をしていました。厳しかったんです。


