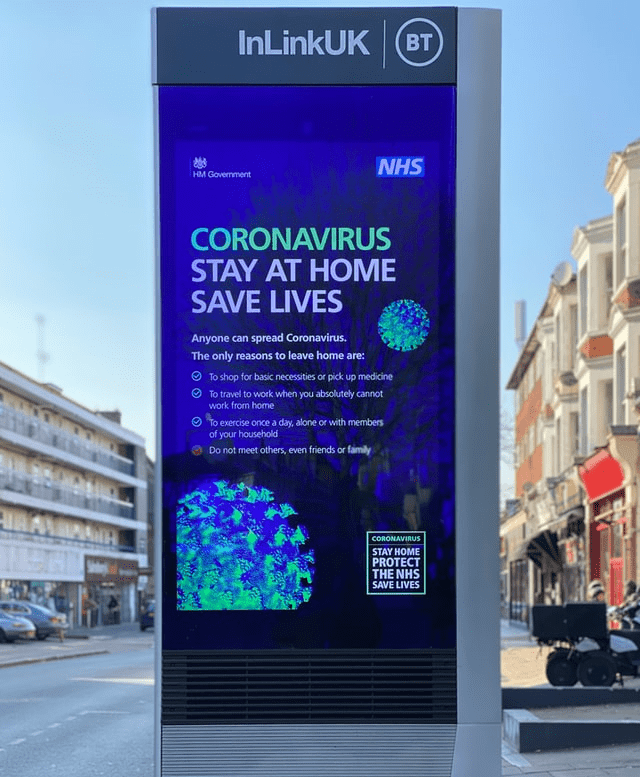おそらく、自分が差別対象だからだと思います。
DAZNの長年の暴力とか本当に酷いんですよ。会社としての鹿島からも、4季の間、酷い扱いでしたし。言いたいことは言いましたが、優勝するための助言しか基本してません。
そこは自信があります。
旧称 twitterで確認した時に、NHKのEテレに忖度している英文学の先生に、え?という扱い(?)を受けたこともあります。知らない先生方なんですが。
一回、興味本位で、本屋さんでとある先生の本を開いて、どうなん?この内容って、英文学で支持なんてとりつけらえへんと思いながら、最後の引用文献などを読んでいて、速攻で本を本屋さんの本棚にもどして、怖いー、怖い―、これで業績って云えんのんかな?軽いホラーになっていると涼しさをいただいたこともあります。
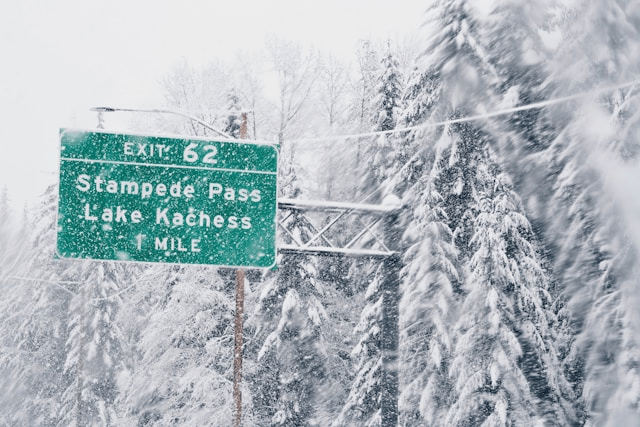
あれは、ホラーでしたね。
知らない先生なので興味ないですが。
どんな教育を受けましたか?ですか?
精読です。
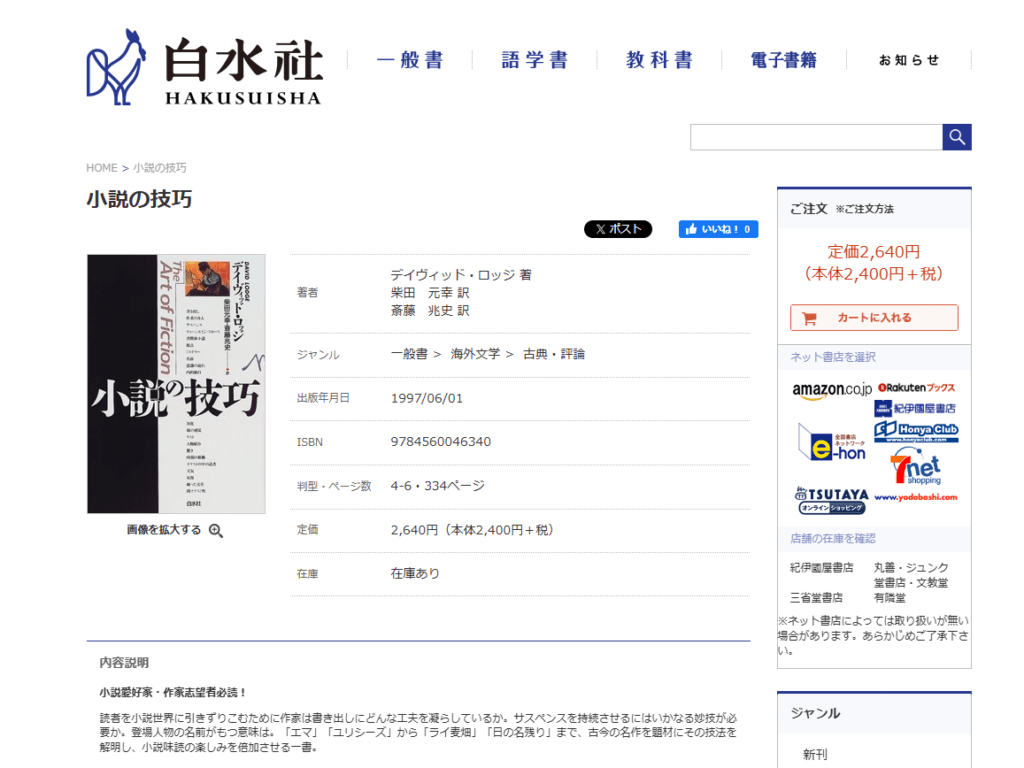
小説の技巧 – 白水社 (hakusuisha.co.jp)
学生の皆さんは、図書館で借りてください。翻訳で十分ですよ。私は原著が教科書だったこともあります。講義を取った当時の学生の私たちが、当たった時にやることは、テクストの内容のまとめの発表と、先生からの鋭い質問にきちんとこたえるという苦行です。
私の先生が、デイヴィッド・ロッジの小説を教科書に選んでくださったことすらあります。
『小説の技法』に書かれてあることは、基本的には「精読とは?」という問いになるので、参考になると思います。
とにかく、読むんです。テクストを。たった1パラグラフを精読をします。訳して理解をして、言葉の運び方を理解して、なぜ、このような言葉の運びになっているのだろうというのをたった1パラグラフで考え込むんです。次のパラグラフにいっても姿勢一緒です。そして、そのまま読み進めて読み終わります。
途中でメモは沢山取りますよ。どうして、ここで”scheme”という言葉が選ばれているんだろう?わからないけど。あ、また、ここでも”scheme”という言葉が選ばれている、誰によって語られた部分でこの言葉が選ばれていたのかな?ここでは、この人だけど、ここでは語り手、うーん、なぜこの単語が選ばれているのだろうか?みたいなことを延々とやります。
再読は必須になります。

まぁ、学部生ならそこまで悩む必要性もないと思いますが。この小説を読むからには、この研究書も、この文献も読むべきというのが後から、わらわらーと出てくるので、それも読みます。
気の合う先生もいれば、それはちょっとどうなんですかね?という先生も出てきます。
ただし、被引用文献数は重要ですし、大体大事な論文って、引用文献ですと、註に、古い文献から、新しい文献まで「これは読むべき」と顔を出すのです。それはきちんとした論文ということです。
自分の興味が出てきたら、他の小説も読んだりもします。
影響なんてあるのかな?ないのかな?影響下なのかな?この作家の姿勢はどうなんだろうとか考えたりもします。
読んで、読んで、読んで、視点を探します。
勉強量だけはあるので、適当に研究書を読むと、それが良書かどうかすぐ判断ができてしまうんです。
たたき上げの読書量だからです。理解できない分野も沢山ありますけどね。
どこかの知らない大学の先生の適当な揶揄に出会うと、うんざりしたりします。傾向性としてざっくりと本屋さんで立ち読みした限りでは、揶揄の傾向性と立身出世に無我夢中という先生ほど、何かを忘れてきている印象をもっています。

本来の日本の英文学は、それを忘れてはという先生は、それらの先生が上っ面で粉飾しているほど、評価対象にはならない強度があるんです。
へぇーって思って終了です。
東大も京大も、大学の肩書きなんて一切役に立たない世界観があるんですよ。優れた先生ほど、え?なんでそこの学校にいるんだろうって学校にいらっしゃったりします。まぁ、居心地の問題なんだと思ってます。使い走り以外の何物でもない時に、東大の先生と、とある大学の先生との大人げない喧嘩を目撃して、逃げ出そうとしても逃げ出せなかったときがあります。とある発表で、発表者を完全無視して、先生同士がいがみ合っていて。発表者の立場がないという。あのときほど、心のやり場に困ったことはありませんでした。使い走りの立場だったので、自分があんな目にあったらどうしようと思ったんですが。自分の先生方がそれほど学生を表立って庇う先生ではないのに後で気づいて、そっと胸をなでおろしたことがあります。