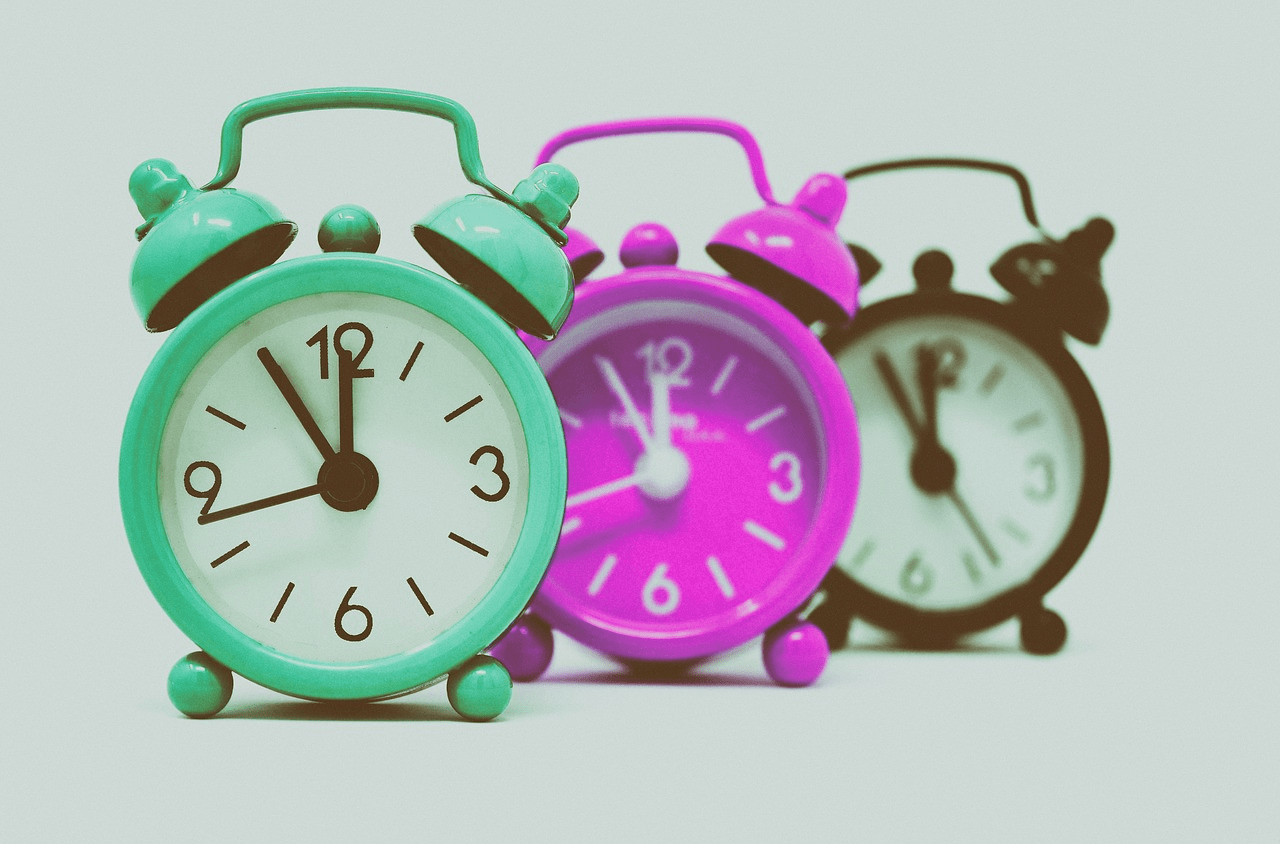中原中也の詩で『サーカス』という有名な詩があるんですが。
私はサーカスに行ったことがないんですね。映画で観たことはあるんですが。
ブランコに乗っているサーカスのひとの視界に、汚れた木綿のサーカスのテントが入ってくるのです。
自分もブランコに乗っているので、視界の遠近が揺れるんですね。
そして、風が吹いているので、サーカス団のテントも揺れるんですね。
それをうまい具合に擬音で表現をしています。
頭倒さに手を垂れて
汚れ木綿の屋蓋のもと
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよーん
中原中也 『サーカス』より
ブランコに乗って揺れるということは、ブランコからも音がしているはずですし、視界に入る外の風に波立っているテントも音を立てているはずです。但し、それらの音は上記の擬音のとおりの音ではないはずです。そこが、詩なんですよね。読み手のイメージに働きかけてくるんです。

これを英語に翻訳するって至難の業だと思います。中原中也が読者に届くように表現したような擬音の工夫が英語圏に存在をしません。
一方で、英語圏の文学で、これは日本語に翻訳しづらいというのもあるんですよ。
小説になりますが。ジョセフ・コンラッドという作家の『闇の奥』という小説があります。主人公のマーロウが、アフリカの奥地に消えてしまった謎の人物であるクルツという人物を探しに行く物語になりますが。
もちろん、私は英語が出来るので、英語で読めます。
マーロウが伝聞として、クルツはこう言っていた、クルツはこういう風貌だったというのを実際の会話の中で伝えるんですね。つまり、語り手の描写という形式は、実際に、会話の中に2重3重に折りたたまれています。マーロウの会話のなかには他の登場人物も出てきます。そして、マーロウがこういう風景を実際みていたんだというのを語る発話のなかでしか、最後のクルツは存在しません。そして、マーロウが注視するのは声なんです。”Kurtz discoursed. A voice! a voice! It rang deep to the very last…..” 「クルツが話をしている。声だ。声だ。それは最後の最後に深く響いてきた。」よく、議論にあがる言葉の手前で、いろんな工夫がなされています。どんな議論があるかというと、アフリカの奥深くで、マーロウが出会ったクルツは既に死に近づいていて、死に際の最後の言葉を聴くことになるんですね。その最後の声は、実際に発話された声なのかどうかという身も蓋もない議論なんですよ。世界中で同様の議論があります。『闇の奥』の作品研究においては。定番の議論になります。ポストコロニアリズムの文学論だと、クルツの最後の言葉である”the horror !”は、西洋がアフリカにみた植民地政策の幻影みたいな大仰な議論にまでなります。
コンラッドが植民地政策を遠景に見ることができうる時代を生きていたかというと、正直、むつかしいです。
“He cried in a whisper at some
image, at some vision—he cried out twice, a cry that
was no more than a breath—
“ ‘The horror! The horror!’…..”Joseph Conrad Heart of Darkness
彼は何かイメージのような、幻像のようなものをみて、息のなかで叫んでいた。ー二度叫んだ。その叫びは息づかい以上のものではなかった。
息と訳しましたが、”a whisper”って、とても静かに発声する声になるので、他人からは何を言っているのかわからないという意味に基本的にはなります。
つまり、クルツが息をしているなかでの発話というのは、実際にマーロウには聞こえていない可能性が高いんです。
その後の、翻訳がむつかしいのが、2度繰り返される”the horror!”です。実際に英語で発話をするとわかるんですが、息のなかに交じりやすい発話になります。息の中で破擦音が生じる感じに近くなると思います。破擦音の拡大解釈として、”the”の発音が聴こえる余地はありますし。そして、余地だけになります。次の “horror” の最初の “h”は、無声声門摩擦音という音声になります。声帯の間から出す息だけの発音なんですよ。”the horror” という言葉自体は息と交じりやすい言葉になります。つまり、実際にクルツが死に際に発話しているのかどうかさえ怪しいということです。ただし、マーロウには、”the horror!”と発話しているように聞こえたんです。マーロウが意図的にそのように聴いたと解釈できる余地はあります。
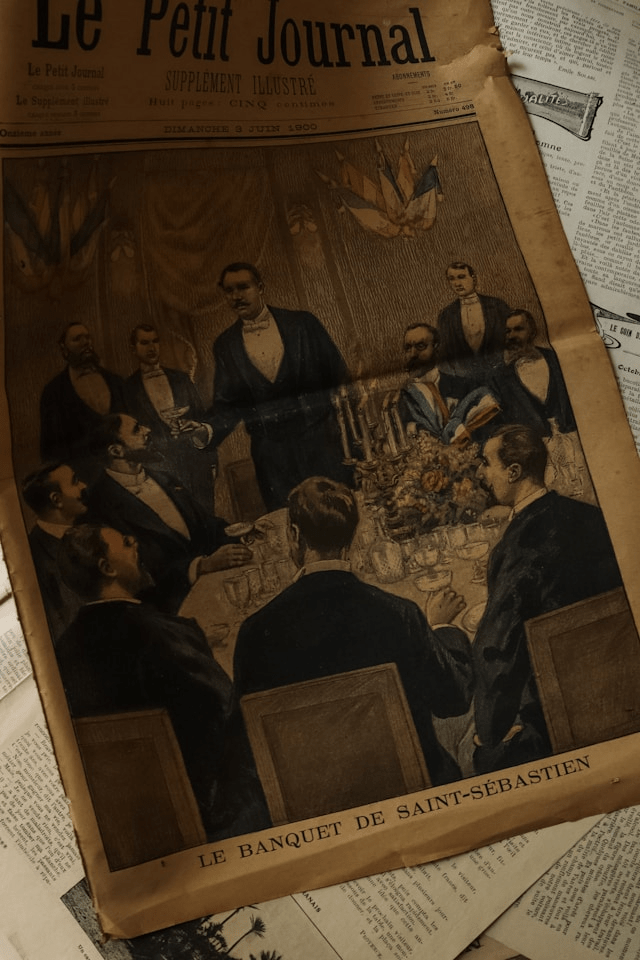
クルツの息づかい以上のものではない死に際の息づかいに、マーロウは、言葉を読み取ってしまうんですね。マーロウ自身が、クルツの声に引き寄せられているというのもあると思います。
今わの際の息遣いのなかで、本当にクルツは言葉を発していたのだろうかという部分が肝になるんですが。
英語の “the horror !” だからこそ成立するんですよ。”the” なのでどんなに低い声でも耳には届きますし、”horror”が、次の言葉なので、息づかいとして成立するんです。
コンラッドって、英語を第2言語として習得をして小説を書いた作家なので、これが成立するんですよ。ポーランド出身で、英語を習得し、実際に船乗りで、イギリス国籍を取得したのちに、小説を書くんです。凄い作家なんですよ。
クルツの死に際のこの言葉を日本語に訳せるかというと、むつかしいです。翻訳は沢山出てますけど。中野好夫先生は、身もふたもなく、「地獄だ!地獄だ!」と翻訳をなさっていたはずです。岩波文庫は中野好夫先生の翻訳です。
死に際にそこまで明快は発話ができないのは、翻訳家としてもご存じだったんだろうなって思うんですね。そして、中野先生ならではの明快さで、クルツが置かれた状況に翻訳をなさっています。
このクルツの死に際の言葉が小説全体を左右するんですが。日本語に翻訳をするうえでのむつかしさを、同時に、提示もするんですね。
翻訳の場合は、ストーリーとしては追えるのですが、言語の壁を乗り越えられないんです。

むつかしいなーって思いますよ。
A.I.や機械翻訳が太刀打ちできないんですよ。文学ですからね。新潮文庫が「地獄だ!地獄だ!」と宣伝をかけてしまうのは、もう人文学のベーシックの底が、新潮文庫で抜けているという事実に基づいているとしか思えないんですよ。段々と、危機を通り越していますよね。文芸を扱う出版社の知識の底が抜けているということです。私はその少し前に徹底的にしごかれているので、出版社の常識の底が抜けている状況を等閑視できますが。どうなんだろうなーとは思っています。発音記号ですか?徹底的にしごかれています。この一文を発音記号におこしなさいというテストが普通でした。厳しい学校だったんです。いい先生方に恵まれたんですよ。うっすい教科書なのに、良識ある先生がそのテクストで講義をすると、何倍もの厚さがあるように感じるんです。実際にそうでした。