☆☆みたいな★★というたとえ話が空回りしているのを目にしたりするときですね。
比喩表現として成立していないのがよくわかったり。
使いこなせていなかったり。
言葉だけぽっかりと浮かび上がってしまい、どことも馴染んでいない状況がとても苦手です。
きっと頼まれ仕事なのには違いないのだろうけれどという読み物があったりするじゃないですか?
研究者が別の分野からの雑文を頼まれて書いていたりするものです。

事前の擦り合わせや、テーマ設定はあるんだと思うんですが。研究者の言葉選びが、普段から雑然としているのかもしれないという雑文に偶然出会ったことがあって。
どうすればいいんだろうか?という気持ちになったことがあります。
どうしようもないので、読み流すしかなかったんですが。
どの研究者と特定をするわけにはいかないので、そこは伏せますよ。
イコンという言葉があります。わたしが最初に書物で触れたのは、中沢新一先生の本です。中沢先生のご著書を網羅的に読んでいるわけではないんです。だって、既に手に入らない本も出ていますし。中沢先生が野心的にお書きになった本で、それは不得意ですと避けている本もあるくらいです。『今日のミトロジー』とかだと、わたしが最近の物事に対してさほど興味がないので。中沢先生はきっと大変なんだとは思うんですが。本屋さんで手が伸びるまでは行きません。
それでも、中沢先生の本のなかで「イコン」という言葉の意味を知り、使われ方を知り、学ぶんですよ。
ふっと「イコン」という言葉がわたしの中から出てくるのに、10年くらい経っていたりします。
馴染むまでに時間がかかったのかもしれませんし。馴染まないと言葉って出てきませんしね。
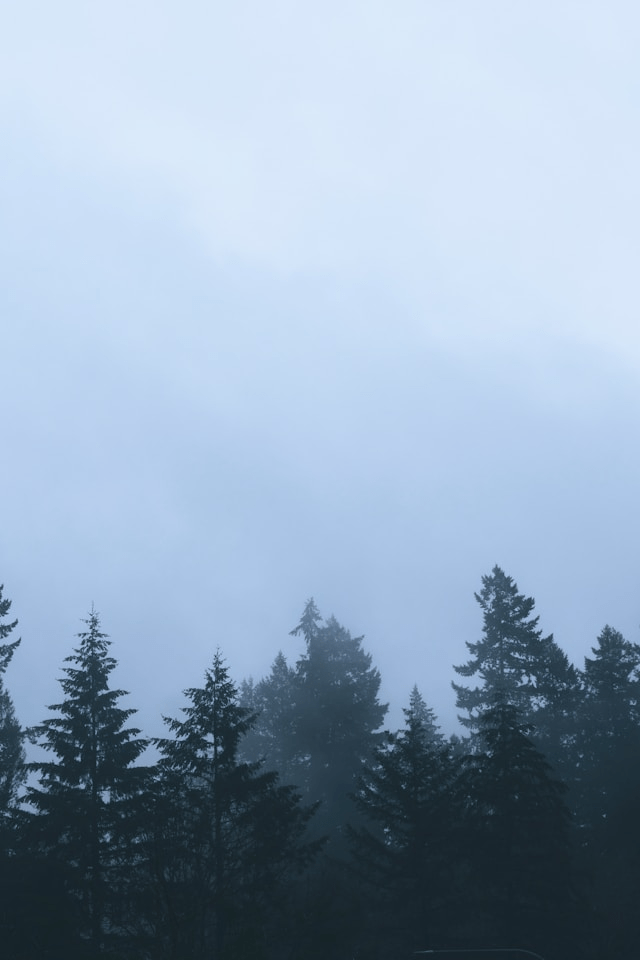
偶然目にした研究者の雑文では、読んでいてもなんだか、持論にことよせるために手続きがかなり端折られていて。読んでいる読者層は軽そうだから、これくらい端折ってもいいのかもという研究者の姿勢がわかりやすく文章になっていて。
寒々しい気持ちになったりもしました。
「イコン」自体、英語だと幅広い意味をもっていたりもします。使う時にはその言葉の揺れ幅のなかで使ったりするんですけど。
矮小化されて言葉が使われている現場を見ると、寒々しい感覚にはなります。
随分以前に、自分の先生に(複数形です)、アメリカ合衆国のキリスト教の在り方について質問をぶん投げられたことがあり、わたしが専門としているのはイングランドの文学で、先生がわたしに質問を投げかけている真意については、アイルランドの文学研究をこなさないと応えられないんだけれどという時が実際にあったんですね。
疲れていたのも手伝って、さぁーどうなんでしょうねー、知りませんって逃げましたけど。

アメリカの映画のなかに投影されているキリストの宗教観だって一筋縄ではいかないのだろうなと思ったりもします。
イングランドの宗教って勉強するだけしんどいというセクトだらけだったりもするので、アメリカ合衆国のような移民の集まりで国の基礎が成り立っていたりすると、余計に理解が困難になるのかもしれないと思ったりもします。
イングランドは国教会ですし。日本人並みに排他的な宗教観を形成しています。
アメリカ合衆国だと、どう排他的になるのか想像もつきません。どこかで蛇口を締め忘れて、水漏れみないな状況もあるのかもしれませんし。
漏れた水が全然違うものと混交してしまうこともアメリカ合衆国の歴史のなかだとあるのかもしれませんし。もうわかりませんよ。

とりあえずと捕まえる学生を間違ってますよ、先生とも言いづらいですし。
一応、先生の所でも学んでいるので。
めんどくさいなーって思う時もありました。
それでも先生が文章をお書きになるときには、暗喩がかなり微に入り細に入り、わたしはわかりませんっというむつかしさが実際にあるので。
逃げるしかなかったりしたのですが。
つまり、どんな雑文だろうが手を抜かないという風景を当たり前にして、学生を長くやったので。
これはどうしたらいいんだろうという雑文に出会うと、こころが寒々と冷え切って、たちすくむみたいな状況になります。
日本の人文科学はどの地点から侘しさを読者に感じさせるまでに消失してしまったんだろうって。
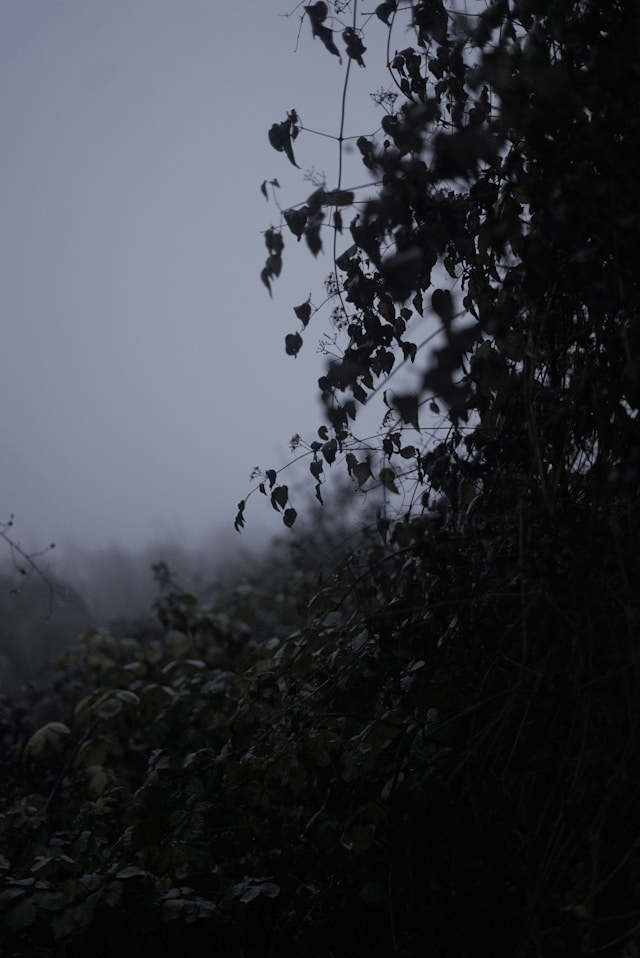
迂闊に文章を読んで寒々しい気持ちを抱えることになるとも思いませんでしたが。
ちょっと困りましたね。
一見、異なっている概念のように見えますが、実はそこにはというときには、きちんとした説明が必要になりますし、読者を舐めるという姿勢は研究者にあってはならないような気もします。誰が読むのかわからないからです。


