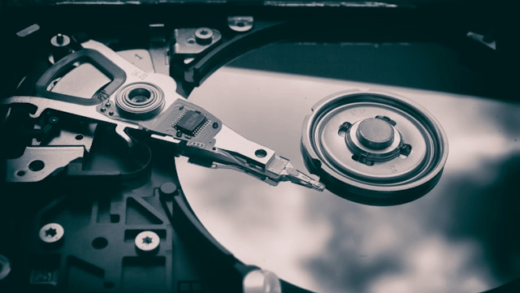個人的なことですが、判断するまでは時間をかける派です。
苦手なことは批判の為の批判です。理由は生産性がないからです。
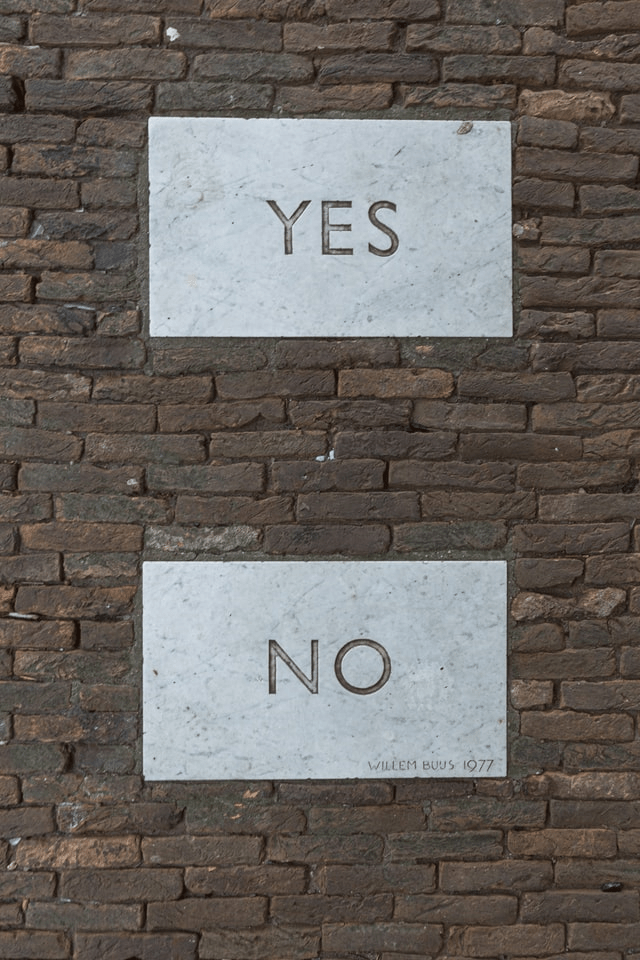
Yes か No かはっきり出来ない時だってたくさんありますが。ただ、Yes or No を求められる時はありますし、決断が重要なときも存在はします。そういう場合は、本能的な反応には従わないようにしています。本能的な反応が案外間違っている場合もあるからです。
いわゆる単なる生理的な反応になっていて、そこに論理性が介在していないので、後々齟齬を生じることになることもあります。
Yes か No かの手前でゆっくりと考えたいときだってあります。
私が精神医療の誤診を受けたときのことを例にとります(日本の精神医療は誤診しても責任はとりませんし、一旦誤診されると、誤解を解くまでに患者にかなりの負担を強いるので、できるだけ避けてくださいね)。
この精神障害が流行った時のことです。

当時の主治医は私の病の原因はこれなんだという判断を下していたようです。例えば、過集中なのではと疑いをかけられていたようです。薬漬けのなかで。
当時からですが、周囲の指摘があるまで過集中に気づかないという症状は正直ないです。集中力が通常の人よりも続くのは、集中力が必要とされる勉強を長期間にわたりこなしていただけです。
当時もいまもマルチタスクはこなせます。
当時の政権が発達障害者のガイドラインを作り支援制度を確立するための施策を出したのですが、そこに心理や日本の精神医療がかなり悪乗りをしていたのだと思います。
正直、NHKがこの企画を立ち上げた当初は、なんでもかんでも発達障害という一種の流行のようになっていました。学問に流行ができるというのは自然なことなのですが、薬物投与という時点から考えたとしても状況は酷かったと思います。
また、コロナ禍も重なって、症例が一概に括れなくなったという現状もあると思います。
精神医療(臨床医)はある程度の技量があっても誤診することがあります。経験済みです。その点に関しては、誤解を患者側が取り除いていく努力というのが必要になるのです。
コロナ禍では「通常であれば」ということが「通常では」なくなります。
学校では給食時間に黙食を生徒さんたちは強いられています。赤ちゃんからご高齢のみなさんまで、通常とは違った状況で多かれ少なかれ生活を強いられることになります。
数年後に、NHKの説明による「発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさ・凸凹(でこぼこ)によって、社会生活に困難が発生する障害のことです」がかなり違った視点で見直されることになるとは思います。
一時期、皇后さまが罹患された「適応障害」については、皇后さまが罹患されたということを履き違えてしまう心理や精神医療の研究医及び臨床医(研究医は本当に多いんです)が日本で多発しました。
調べましたが、皇太子妃殿下だったとき、現令和天皇のもとに嫁がれる前は、皇后さまはバリバリの外務省のキャリアだったのだそうです。環境がだいぶ変わってしまい、私が想像もつかないことが沢山重なって、そのようなご病気を経験なさったのだと思います。
それと、一般の人たちが経験する「適応障害」にはかなりの落差があるはずです。
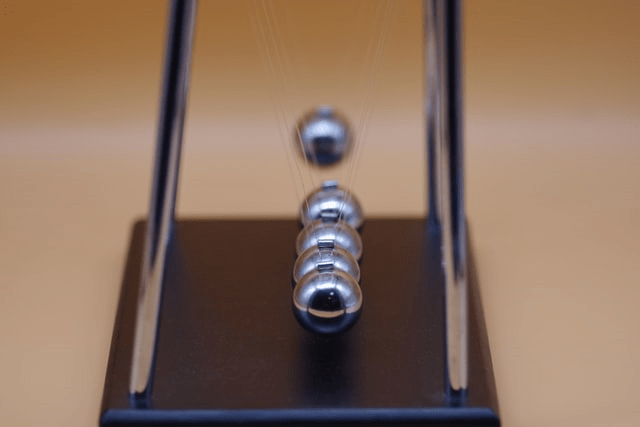
元鹿島で、いまスペインで頑張っている柴崎選手が、鹿島から逃げた先で、どよーんとなってしまい、「適応障害」のハンコを主治医の先生に押されたことがあったんです。いまではスペイン語が堪能なので信じられませんが。急に居住空間が鹿島から違う国に変わって食生活も何もかもがすべて違えば、そうなる期間があったとしても私は自然だと思うんです。
当時の代表戦に召集された後に、試合後のフラッシュインタヴューで「適応しますっ!」って発言していて、こっちが悲しくなったことがあります。
だって、それは義務ではないからです。義務感が伴うと余計な抑うつ感を抱え込むことになりますから。サッカーという仕事をするにはチーム内でのコミュニケーションは必要なのかもしれませんが。鹿島とスペインでは、またその内容は違いがあるのかもしれませんし。柴崎選手はもうコツをつかんだんです。
また、東京に進学した大学生が、標準語に染まらないと「東京に適応できていない」と「適応障害」のハンコを押されるという話はあんまり聞きません。
ただ、コロナ禍のなかでは、主治医の先生が病名はカルテに記載しないといけないので「適応障害」とハンコを押すのかもしれません。
通常だったら、進学当初から大学は開いていて、普通に通学できて、友達もできてというところがむつかしいのですから。
これは変だなぁー、何回も考えたけれど、おかしいなぁーって思う気持ちが大事になります。
「適応障害」の場合はストレスの原因が明らかで、それと距離を置くと元気を取り戻せるそうです。
最初に病名で流行させて、あれこれ齟齬が出るということで、病名の分類がのちに分類しなおされるというのは、日本の精神医療ではよくあることです。本当なら、最初に誤診がないほうが望ましいのですが。
通院を考える手前でたくさんの気分転換を考えてくださいね。
よく認知の歪みって聞きますが、認知の歪みって日本の精神医療の研究医のほうが沢山抱え込んでいますから。
ああ、この先生は日本の社会生活は「高校」止まりのものが延々と続くと誤解していて、日本の社会構造の認識に対しては90年代でずっと止まったままなんだという研究医もいるんです。
コロナ禍で日本でも自殺率上がったのですが、日本の精神医療が事前に啓発に乗り出した話なんて聞いたこともありませんし、それに対して事前に構造的に対処したという話もありません。
日本の精神医療はどこかいびつなんだと思います。
おそらく先進国のなかでも日本の心理及び精神医療(特に研究医)ってレベルが高いとは言えないのかもしれません。研究医のTwitterって病んでるものも少なくないんです。アカウント画像が2次元アニメだったりする先生もいます。診察受けたいかというと絶対に嫌ですね。