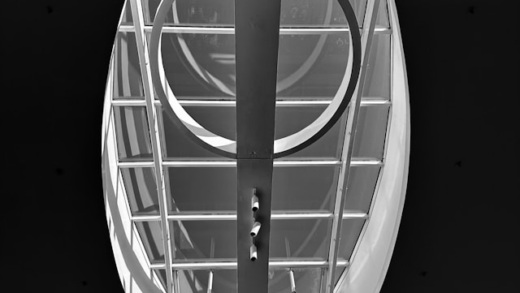YouTubeって世界展開なので、いろんな情報がありますよね。
アレクサの限界の記録を観たことがあります。
私はアレクサを使ったことがないので、実際、日本語でどのような運用がなされるのか知りません。
こんな感じの可哀そうなアレクサの記録だったんです。
Johnさん:アレクサ、削り粉があまってんねんけど、レシピなんかない?
Alexa:まかないのレシピは豊富にあります。調べましょうか?
Johnさん:??
Alexa:最近、人気のまかないレシピは「地鶏のシチリア風ロースト」です。材料は・・・。
Johnさん:アレクサっ。削り粉があまってんねんけど、レシピなんかあらへんか?
Alexa:ちょっとわかりませんでした。
Johnさん:(溜息)アレクサっ。削り粉があまってんねんて。それを使ったレシピがないか聞いてんねん。
Alexa:天然素材をつかったレシピについてはたくさんあります。醤油は、大豆を元に作られた加工食品で(うんぬんかんぬん)。
Johnさん:(話をさえぎる)アレクサっ。(ぶつぶつと)削り粉があまってるだけやのに。賞味期限せまってるだけやのに。Alexa、削り粉を使ったレシピを教えてくれへんか?
Alexa:(沈黙)
こんな感じですが。アレクサって英語圏では大変みたいなんです。標準の発音に対して回答できるような基本設定になっているみたいで。

アメリカの会社で開発がなされていますから。むつかしいのでしょうが。
英語の母国であるイギリスでは、本当にさまざまなアクセントが用いられています。それぞれの地方の独自の言語の運用もあるくらいなので。
アレクサくらいだと歯が立たなくなるみたいです。
むつかしいなぁーと思いました。
購入したひとからすると便利だと思って使用しているのに、アレクサの仕様から、英語の母国であるにも関わらず、言葉が判読できなくなるそうです。

サッカーだと、セルティックFCの元監督が前オーストラリア代表のポステコグルー監督だったので、日本人が、大人数で在籍をしています。ポステコ監督はセルティックFCに行く前は、マリノスの監督でしたし。
スコットランドの皆さんの温かさはよく理解しています。
たまに、大丈夫なのかな?と思うこともあるんです。
セルティックFCの公式の動画で、日本国籍の選手が、英語もしゃべらずに、お互い会話をして、そこに英語字幕をつけたものを挙げたり、また、試合後には通訳をつけていただいていたりしています。
それでいいのだろうかと、個人的には思ったりもします。
新しい監督は元レスターのロジャーズ監督です。セルティックとしても相応しい監督を引き抜いたなぁーとは思いますが。
イングランドのリーグと、スコットランドのリーグは別のリーグになるので、むつかしいところになります。
そこまで好待遇だと、他の国籍の選手から異論はでないんだろうかと不安になることもあります。
鹿島はもちろん、外国籍の選手には通訳をつけますが。ブラジル国籍の選手は、日本に馴染もうと普段は少し日本語を理解しようと頑張っていたりもします。選手同士のコミュニケーションは必要になります。ナイジェリア国籍の選手は英語の通訳ですし、韓国籍の選手にも通訳はつきますが、ポジションがキーパーになるので、スンテ選手くらいベテランになると、凄いなぁーという感じで日本語でみんなを笑顔にしてしまうスキルまで習得済みです。

英語を頑張っている日本人選手も少なくないと思いますが。
その厚遇はスコットランドのリーグだからあり得るのであって、隣のプレミアリーグでは皆無であるという現実をみる側面も持ってくださいね。
サッカーで機械が介入できるのはVARくらいで、VARも結局、VAR班による視認のための道具でしかありませんし。
毎日の生活も大変な側面があると思いますが。
頑張ってくださいね。
ちなみに英語は、欧州の言語のなかでも比較的習得しやすい言語になると思います。
アクセントの問題は、隣のプレミアリーグでも、実は同じなんですよ。
スコットランドのBBCのコメディーリリーフで、あーというのをみつけて、簡単に笑顔になれないーっと思ったことがありました。設定としては、アメリカ人の乗客を乗せた飛行機のパイロットがダメになり、乗客がなんとか飛行機を軟着陸させようとしているんです。場所はスコットランドです。管制塔ではなぜか地元の言葉が使われていて、軟着陸ですか?専門のひとがいるんで引継ぎしますねと引き継がれた先が俳優のジェイムズ・マカヴォイさんです。バリバリのスコッツです。ここまで理解できるけど、ここから理解できへん。あ、飛行機を軟着陸させようとしている乗客も理解できてない、アメリカ人の設定だから無理っ。実は、日常の動詞や名詞、つまり、品詞の運用がすでに、イングランドと異なるんですね。そのまま、軟着陸もできず、引き継がれる管制塔の地元の言語は、ウェールズになるんです。待って、待って、間にイングランド横たわってるはずやろ、地図上では間にイングランドがあるはずやけど。どういうことなん?ってなりました。随分以前にスコットランドに行ったときに、Highlandに行ったらいいのに、景色がすごーくきれいだよって勧められたことがあるんですが。Highlandになると言葉が部分的に英語でなくなるので、どうしようーって思って結局行かずじまいでした。卵も単語が違うそうです。宿泊先の皆さんに迷惑がかかることが事前に予想できたので。景色は観たかったんですけれど。むつかしいですね。英語に関しては、きちんとスコットランドの英語があり、スコッツがあり、後はその地域地域の言語運用になります。すいません。もう一回いいですか?こういう意味ですか?どうしたらいいですか?と聞くと、丁寧に説明をしてくださるのが、スコットランドの人の気質みたいです。大きな額の紙幣が余ったので、お店で買い物をして清算しようとしたときに、驚かれたことがあります。買い物自体は必要なものだったんですが。当時は意味が分からなかったんです。「この紙幣しかないの?」って聞かれて、「そうなんです。細かい紙幣を使い切ってしまって」と応えると、お店のひとは結構な時間悩んで「紙幣が大きすぎてお釣りがだせないんだよ」と返事を返してくれたんです。ぼーっとしたFar Eastの人間が結構な金額のお札を商品を買って両替しようとしているからです。見るからに偽札なんて持ってなさそうなのは明らかです。「どこに行ったらいいんでしょう?」と聞くと、結構思い切った応えが返ってきました。「銀行で両替をしてくれるから。銀行に行ってみたら?」と丁寧に道を教えてくれて、行くと結構豪華な主要銀行の支店でした。普通に両替をしてもらい、そのまま、お店に戻って、買い物のレジを訪れて驚かれたことがあります。意味が分からなかったので笑顔で「両替してもらえました。ご親切にありがとうございます」と挨拶をすると、安心なさったのか「それは、よかったねぇー」と応えてもらったのを覚えています。常識がわからないとそんなことにもなります。